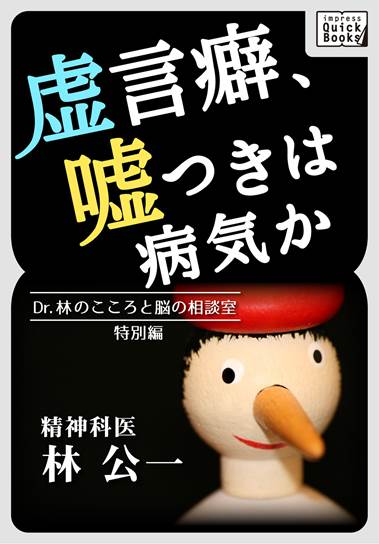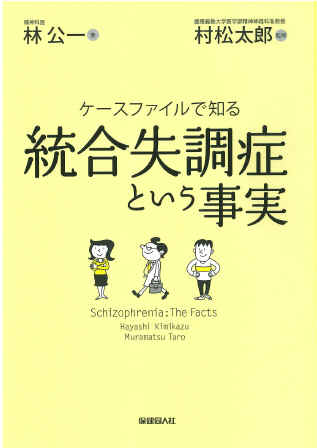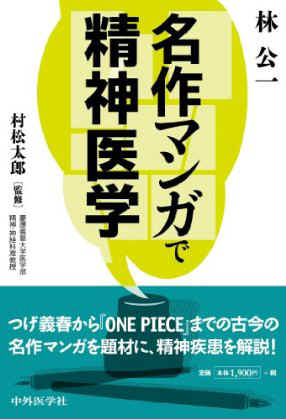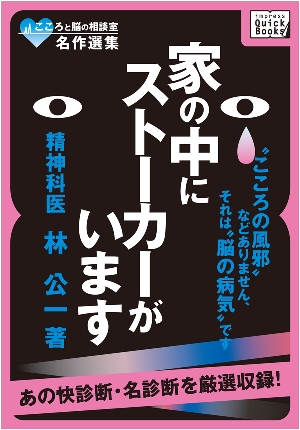【4971】本当の自分はラモトリギンを飲む前の自分か飲んでからの自分か
Q: 30代女性です。小学4年生から不安障害に悩まされてきました。大学生になってからは鬱々として夜眠れなかったり、朝起きられなかったり、人に会うのが苦痛で大学をサボることもありました。趣味の音楽のサークルでさえも、怖くて練習に行けないことがありました。これは社会人になってからも続きました。朝がとにかく憂鬱でなかなか布団から出られませんでしたし、夜は疲れて眠いのに、人生の全てが苦痛に感じられ眠ることができませんでした。職場では人の目が怖くて、失敗するのが恐ろしく、上司や先輩に質問するにもビクビクして、前にも後ろにも進めないような絶望的な気分で毎日過ごしていました。
8年くらい前にレクサプロを飲み始めたのですが、開始から1週間後くらいからものすごくハイテンションになって、世界がキラキラ輝いて見えました。普段は大学をサボるくらいですから、休日も引きこもりがちなのに、2、3週間くらい遠方に出かけまわりました。疲れがあってもそれを上回るほど動き回りたくてあちこち行きました。その後は自然に落ち着いていき、同時に不安が以前より取れていることを感じました。ハイテンションになったことは医師にはあいまいにしか伝えませんでした。できればずっとハイテンションでいたかったのと、不安も取れていたので、レクサプロをやめさせられるのが嫌だったからです。
半年ほど前の話をしたいのですが、その時点での処方はセルシン2mgを3回、レクサプロ20mg、睡眠薬としてベルソムラ15mg、クエチアピン10mgでした。
会社関係の人に、あなたは双極性障害ではないか?と指摘されたのです。それを医師に伝えたところ、「ラモトリギンという薬は出せますが、僕は必要ないと思います」と言われました。(この医師はレクサプロを出した人とは別です。) しかしレクサプロでハイになったこともあって、とりあえずラモトリギンを飲んでみることにしました。ラモトリギンを飲み始めてから、鬱々とした気持ちや不安が激減しました。朝もすっきり起きられるし、夜もよく眠れるし、人の目もそんなに気になりません。それから、私は歩くことがものすごく嫌いだったのに、何も感じなくなりました。何故かわかりませんが歩くのがすごく苦痛でイライラして不快で、1メートルも歩きたくないくらいでした。でもそれもなくなり、普通に歩けるようになりました。同じように人混みも嫌いでしたが、それも平気になりました。今はラモトリギンは200mgで維持しています。
先日、躁転のようなことがありました。会社で鼻歌を歌ったり、夫に理不尽にキレてしまったり、急に断捨離をしたりしました。家事もすごく捗りました。エビリファイ12mgを2週間くらい飲んだら収まってきました。エビリファイを初めて飲んだ時は30分くらいでスッと心身が落ち着く感じがあり驚きました。
そういえば、睡眠薬としてクエチアピンが出た時も、頭がスッキリして眠れるようになる感覚がありました。私はもともと潜在的に双極性障害だったのでしょうか。引越しが多く、いろいろな医者から不安障害だと言われていたのですが。
ところで、本題はここからで、【3868】コンサータによって自己の連続性を失いつつある と同じような内容になるのですが、本当の自分は何なのか?という疑問が生じ始めました。
x軸とy軸があって、x軸は健康的に元気な自分と、健康的に落ち込んだ自分を表しているとします。y軸は病的に元気な自分と、病的に落ち込んだ自分を表しているとします。レクサプロやラモトリギンを飲む前の自分は、x軸がマイナスだったのか、y軸がマイナスだったのか。つまり、単に根暗で心配性で臆病なだけの人だったのか、それとも病気としての不安や鬱で動けなかったのか。ラモトリギン服用後の爽やかに生きられる感覚は、x軸がプラスに転じたのか、それともy軸方向がプラス、すなわち躁転の性質を有するものだったのか。自分の原点はどこにあるのか。ニュートラルな自分とは何なのか。
私は物心ついた頃にはすでに根暗な子供だったと思います。人前で挨拶をしたり、発表したりするのが怖くて、すごくエネルギーを使いました。これは元来の性格としてネガティブということなのか、それとも実は幼少期から病気だったのか。きっと実態としては、性格と病気と両方あるのでしょうし、そもそも判別のしようもないのでしょう。すなわち、幼少からラモトリギン服用前まではxもyもマイナスだったと考えるべきなのだと思います。では、ラモトリギン服用後の、夜によく眠れて朝にすっきり起きられて、人混みを歩いても平気な自分は何なのでしょうか。xがプラスに転じたのか、それともyがプラスに進み始め、結果として会社で鼻歌を歌うようになってしまったのでしょうか。そもそも、xとyは単にプラスかマイナスかだけで語れるのでしょうか。「私」という存在は、xy平面上に存在する円のようなもので、その円の中には、全ての象限が含まれているのではないでしょうか。xがプラスの自分もマイナスの自分も、yがプラスの自分もマイナスの自分も、全て含めて「今この瞬間の私」なのではないでしょうか。なんだか自問自答のようになってしまいましたが、先生の見解が聞きたいです。
林:
私はもともと潜在的に双極性障害だったのでしょうか。
まずこの問いにお答えしたいと思います。回答はイエスです。より正確には、「潜在的に双極性障害だった」ではなく、「(「潜在的」でなく、そもそも最初から)双極性障害だった」が医学的に正確な記述になります。
いろいろな医者から不安障害だと言われていたのですが。
双極性障害でも、あるいは統合失調症でもそうですが、当初はうつ病や不安障害などと類似した症状で始まることはよくあります(【4969】もその一例です)。そして何ヶ月あるいは何年かたつうちに、双極性障害や統合失調症の症状がだんだんはっきりしてくるというのは一つの典型的なパターンで、【4971】のケースはこのパターンの一例であると言えます。もっとはっきり言えば、ごく平凡な一例です。
8年くらい前にレクサプロを飲み始めたのですが、開始から1週間後くらいからものすごくハイテンションになって、世界がキラキラ輝いて見えました。
抗うつ薬を飲むことでこのようにかなり明確なハイテンションになるのは、双極性障害にしばしば見られる特徴です。振り返ってみれば、この時点でこの【4971】のケースは双極性障害とほぼ確実に診断できたと言えます。
ハイテンションになったことは医師にはあいまいにしか伝えませんでした。できればずっとハイテンションでいたかったのと、不安も取れていたので、レクサプロをやめさせられるのが嫌だったからです。
これも双極性障害として一つの典型的なパターンです。すなわち、躁状態であることが主観的には快適であるため、医師にはご自分の状態を正しく報告しないというパターンです。
その後は自然に落ち着いていき、同時に不安が以前より取れていることを感じました。
双極性障害の方が抗うつ薬でハイテンションになった後は、そのハイテンションがさらに高まり、躁状態の治療を要するようになる場合もあれば、この【4971】のケースのように、比較的落ち着いた状態になる場合もあります。但し、少なくとも統計的には、双極性障害のうつ状態には、抗うつ薬よりもラモトリギンの方が有効ですので、ラモトリギンを開始するのは理にかなった治療です。現にこの【4971】のケースでは次のようにラモトリギンが著効しています。
ラモトリギンを飲み始めてから、鬱々とした気持ちや不安が激減しました。朝もすっきり起きられるし、夜もよく眠れるし、人の目もそんなに気になりません。それから、私は歩くことがものすごく嫌いだったのに、何も感じなくなりました。何故かわかりませんが歩くのがすごく苦痛でイライラして不快で、1メートルも歩きたくないくらいでした。でもそれもなくなり、普通に歩けるようになりました。同じように人混みも嫌いでしたが、それも平気になりました。今はラモトリギンは200mgで維持しています。
これは双極性障害にラモトリギンが教科書通りの効果を発揮した例ということができます。そして、当初の不安障害という診断からここまでの全経過は、結果として見れば、双極性障害としてかなり平凡な経過であったと言えます。今後もラモトリギンを飲み続けることで、安定した状態が維持されることが十分に期待でき、ひとことで言えば「双極性障害にラモトリギンが著効した平凡な一例」ということになります。
【4971】について、医学の教科書的な説明はここまでです。
しかし【4971】の質問の主眼はそんな教科書的なことではなく、本題は質問文の通り、まさにここからです。
ところで、本題はここからで、【3868】コンサータによって自己の連続性を失いつつあると同じような内容になるのですが、本当の自分は何なのか?という疑問が生じ始めました。
【4971】全体を通してみますと、「本当の自分は何なのか?」という問いは、
(1)私を思う私とは何か?
(2)人工的に脳の状態を変えることは、どんなときに、どの程度まで、容認できるか?
という二つの問いに帰着するでしょう。
先に(2)から行きたいと思います。
(2)は、質問者も言及されている 【3868】コンサータによって自己の連続性を失いつつあるのテーマにかなり重なるものです。したがって回答も【3868】の回答とかなり重なることになります。【3868】の回答から、少々長く、一部を転記します。
このように【3868】の質問者が「自己の連続性」というキーワードで言っておられる内容は、「薬を飲んでいるときの自分」と「薬を飲んでいないときの自分」の「連続性」と言い換えることができるでしょう。そしてそこからの次の段階として、
メチルフェニデートが、脳に働きかけているという科学的な事実が、この精神の変容という事実と合わさることで、脳=精神という、明確な結論を導き、その結論に向き合うことで非常に動揺しております。
という質問者の思考展開は、一方で質問者の深い苦悩を、他方で深い洞察を映し出しているといえます。(この種の議論では、質問者のいう「脳=精神」の「精神」は、「こころ」と表現されるほうが一般的ですので、以下では「こころ」と言い換えることにします)
脳は物質であって、化学的・電気的などの活動で成り立っているのはもはや確定的な事実ですから、こころが脳から生まれることを認めるのであれば、こころもまた化学的・電気的などの活動から成り立っていることを認めざるを得ません。【3868】の質問者が、
精神の座が脳であることなど、言わずとしれた常識なのですが、いざ、それが明確な形で体験されると、私は、あらゆる現象が、所詮は中枢神経の発火に過ぎない
と言っておられるのはそのことを指しています。そして質問者は、
あらゆる現象が、所詮は中枢神経の発火に過ぎないという絶望感=「副作用」を毎日、毎日、経験しているのです。
と苦悩しておられます。【3868】の質問者にはコンサータの服用によってこの苦悩が生まれたわけですが、全く同じ問題は他のすべての向精神薬の服用でも生まれ得るわけですから、この問題は、この回答の冒頭で申し上げた通り、精神科の薬による治療の根底にあって、しかし普段は触れられることのない非常に深いテーマにかかわっています。
【3868】の質問者が「自己の連続性」というキーワードで表現されていた内容は、視点は異なるものの、【4971】の「本当の自分」というキーワードと同一であると言うことができます。そしてこの二つのキーワードは、精神科の臨床的には前述の (2)人工的に脳の状態を変えることは、どんなときに、どの程度まで、容認できるか? という問いに収斂します。「精神科の臨床的には」といま言いましたが、逆に、精神科の臨床から必然的に発生する (2)人工的に脳の状態を変えることは、どんなときに、どの程度まで、容認できるか? という問いが、「自己の連続性」や「本当の自分」という問いに収斂する、と言った方が正しいかもしれません。【3868】の回答の冒頭もこのことに言及しています。
この【3868】のご質問は、精神科の薬による治療の根底にあって、しかし普段は触れられることのない非常に深いテーマにかかわっています。
私は、いっそ、コンサータ を飲んでいる時が、真の私であり
この一文がまさにそのテーマを要約するものになっています。 つまり、コンサータに限らず、向精神薬(精神に作用する薬はすべて「向精神薬」といいます。以下、この回答内での「薬」は向精神薬を指すことにします)を飲むことで精神状態が改善・安定しているとき、では「真の自分」とは、薬を飲んでいるときの自分なのか、それとも薬を飲んでいないときの自分なのか、という問題です。
精神科の治療によって病気が改善することは喜ばしいことでしょう。しかし、治療とは何らかの人工的な作業であり、精神の病とは脳機能の何らかの変調ですから、精神科の治療とは人工的に脳の状態を変えることにほかなりません。この冷徹な事実を直視したとき、すなわち、「治療」という言葉の背後にある「人工的に脳の状態を変える」という現実に直面したとき、ではそれが容認できるのはどんなときで、どの程度までか、という問いから逃れることはできません。「人工的に脳の状態を変えることはいかなる場合にもいかなる程度であっても容認できない」というのも一つの考え方ですが、もしその考え方を是とするのであれば、精神科の治療はすべて行うべきではないという結論になります。それは抽象的・理論的にはともかく、現実的にはあまりに極端で非現実的と言わざるを得ないでしょう。
このとき、ひとつの、わかりやすく、また、直感的にも受け入れられやすいのは、「病気」と「性格」を区別することです。【4971】の質問者の「x軸」と「y軸」もその一例です。
x軸とy軸があって、x軸は健康的に元気な自分と、健康的に落ち込んだ自分を表しているとします。y軸は病的に元気な自分と、病的に落ち込んだ自分を表しているとします。
つまりy軸は「病気」の軸であるのに対し、x軸はそれ以外の軸ですから、何か一つの単語で表すとすれば「性格」の軸ということになります。【4971】の質問者自身が、x軸のマイナスを「単に根暗で心配性で臆病なだけの人だった」、y軸のマイナスを「病気としての不安や鬱で動けなかった」と表現しておられる通りです。
そしてラモトリギンによる改善が、
xがプラスに転じたのか、それともyがプラスに進み始め、結果として会社で鼻歌を歌うようになってしまったのでしょうか。
のどちらであったのかと、という問いに苦悩しておられます。
この問いは、【3868】にしても、【4971】にしても、薬による改善というご本人の体験があったからこそ真剣にお考えになるに至ったという経緯です。そうした実体験がなければ、普通はそういう問いは発生しないものです。【3868】の回答にこう記した通りです。
この問題は、この回答の冒頭で申し上げた通り、精神科の薬による治療の根底にあって、しかし普段は触れられることのない非常に深いテーマにかかわっています。
私は、今まで、脳と精神を分離して考えてきました。
これは【3868】の質問者に限らず、ごく普通の考え方です。逆に、「こころ(精神)とは、結局は物質の活動にすぎない」などということは普通は考えません。
「脳は物質である」「こころは脳から生まれる」、そこまでは漠然と認めていても、そこからの三段論法で必然的に生まれる「こころは物質から生まれている(【3868】の質問者の表現を借りれば「所詮は中枢神経の発火に過ぎない」)という結論については、人は考えることを避けているというのが普通です。そして向精神薬によってこころが変容するという事実を実体験することで、この「普通」が破壊されるとすれば、向精神薬は黒船的存在であると言うこともできるでしょう。【3868】の質問者にとってのコンサータがまさにそうであったと言えます。
けれども多くの場合は、病気による苦しさが薬によって改善したというプラスが非常に大きいこともあって、そんな小難しい理屈は考えないか、仮に考えたとしてもすぐに考えを抑制してしまうことが大部分です。
薬による改善という実体験以外に、この問題を人々に真剣に考えさせるもう一つの場面は、犯罪です。犯罪が発生したとき、端的には、それが犯人の性格によるものであれば犯人は最大限まで非難されるのに対し、犯人の病気によるものであれば犯人への非難は一定程度軽くなるのが常です。これが非常に鋭く現実化した最近の例が京都アニメーション放火殺人事件 で、この事件は被害妄想によって形成された動機によってなされたことは明白ですが、裁判所は、病気の影響はほとんどなく、放火殺人は彼の性格によるものであるとすることで死刑判決を下しています。
京都アニメーション放火殺人事件の裁判所の判断の是非はともかくとしても、そもそも「病気」と「性格」を二分するという考え方は、それが直感的にはかなり受け入れやすい考え方であっても、脳科学的にはかなり異様な考え方です。なぜなら、(精神の)「病気」も「性格」も、脳の機能の現れであるという意味では区別することはできず、すなわちどちらも脳機能の標準からの何らかの偏りないし逸脱であるという意味では同じだからです。【4971】の質問者がこう述べておられる通りです。
「私」という存在は、xy平面上に存在する円のようなもので、その円の中には、全ての象限が含まれているのではないでしょうか。xがプラスの自分もマイナスの自分も、yがプラスの自分もマイナスの自分も、全て含めて「今この瞬間の私」なのではないでしょうか。
これでおそらく、不十分ながらも、【4971】の質問者への回答ということになると思います。「「私」という存在は、xy平面上に存在する円のようなもので、その円の中には、全ての象限が含まれている」、その通りだと思います。少なくとも脳科学的にはその通りです。では社会的にはどうかというのはまた別の問題です。X軸とy軸を区別しなければ、すなわち、性格と病気を区別しなければ、いかなる犯罪者も非難することはできないでしょう。また、脳を人工的に変化させるいかなる治療も容認することはできないでしょう。このうち、犯罪者非難については社会が、法が、決める問題ですが、治療については、基本的にはそれを受ける本人が決める問題でしょう。いま「基本的には」と言ったのは、病気の症状によって他害行為が発生する場合は、また別の次元で考えなければならないということを含意しています。それを別とすれば、(2)人工的に脳の状態を変えることは、どんなときに、どの程度まで、容認できるか? を決めるのは、その治療を受ける自分ということになるでしょう。
現実的・臨床的には答えはここで一応完結します。
しかし、前述の(1)の問いがここでクローズアップされることになります。
(1)私を思う私とは何か?
という問いです。「その治療を受ける自分」というとき、その「自分」とは、薬を飲む前の自分なのか、それとも飲んでからの自分なのか? 結局【4971】のタイトルの 本当の自分はラモトリギンを飲む前の自分か飲んでからの自分か という問いに回帰することになります。精神に作用する薬について考えると、どうしてもこの問いから逃れることはできません。そうしますと、余計なことは考えず、薬を飲んで治ったら、「治った」と喜んで、そこから先は考えない方が幸福なのかもしれません。誰にとっての幸福? もちろん、「自分」にとって です。
(2025.7.5.)