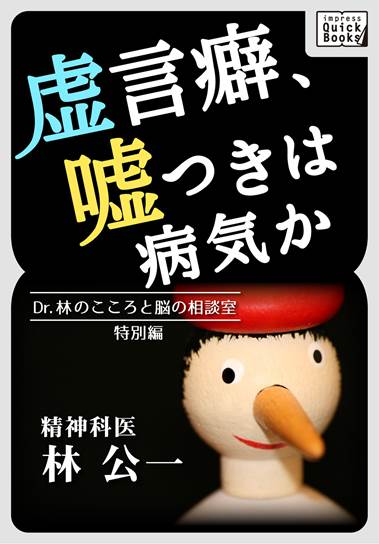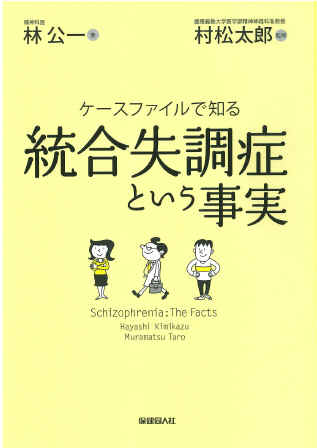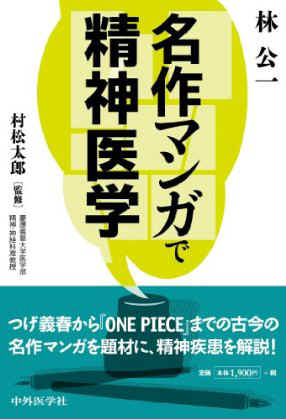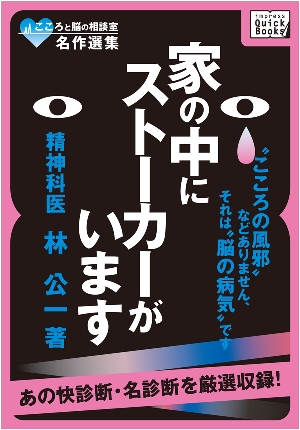【4991】ADHD から双極性障害Ⅱ型へと診断が変わり困惑しています
Q: 30代前半女性です。
「精神科Q&Aに質問される方へ」に目を通した上で、相談させていただきます。
2年前、ADHDの懸念があり現在のクリニックを受診し、心理検査により不注意傾向が強いことでストラテラの服用を開始しました。
不注意が劇的に改善することは無かったのですが、1年ほど服薬し「強い自責思考や自己否定」「周囲からどう見られているかを異常に気にする」「過去の後悔が思考を占有する」回数が劇的に減り、比較的快適に過ごせるようになりました。
クリニックを受診した目的が、ADHD的困り事の解決というよりも、それに関して異常に落ち込み続けてしまう精神面を何とかしたかったので、副作用の便秘以外は服用に満足していました。
また、幼い頃からほぼ毎日起こっていた原因不明の腹痛も、ほぼ無くなり身体的にも負荷が減りました。(腹痛に関してはいくつかの病院で血液検査や大腸検査を数年おきにしていましたが異常なしとのことでした)
また、私はこれまで、1~3年ほどでどうしても会社に行けなくなり休職・転職する、ということを繰り返してきました。
具体的には、朝動悸が酷く起きられない、手足を動かせなくなる、動悸の頻発や勝手に涙が出てきてしまう、業務中自分が何をしているのか分からなくなり思考停止してしまう、などの症状が出てきます。
職場を変えると、また1~3年ほどは働けるようになります。
(今は治っていますが、20歳頃からPTSDやうつ状態だったため、それもあり調子の悪い日が多かったです)
しかし、休職したいとクリニックの先生に相談し、これまでも1~3年ほどで転職を繰り返してきたことを伝えたところ、「ADHD症状が改善していないのであればストラテラはやめましょう。腹痛を抑える作用もないです。以前のカルテに「躁に注意」とあったため、そのエピソードと併せて双極性障害2型の可能性があります」と言われました。
休職し、薬はラツーダとロフラゼプ酸エチル、整腸剤に変わりました。
ストラテラ服用時と大きく変わらず異様な不安に苛まれることはなく、腹痛と動悸は数日に1度出るくらいで収まっています。
前置きが長くなり申し訳ありません。今回ご連絡したのはこの双極性障害2型という診断に納得できておらず、林先生でも同様の診断をされるでしょうか?とお伺いしたいためです。
主治医が双極性障害2型と診断した理由として以下があるそうです。
・周期のあるうつ状態
・ストラテラ服用ひと月後に「良く仕事ができるようになった」とよく喋る日があった
・趣味でイラストや同人誌制作をしている(精力的である)
しかし、双極性障害2型の症状で見られるような短期間の躁状態に私も家人も心当たりがなく、同人誌制作は年1~2回のみで精力的と言えるほどでもない(躁状態と捉えられるほどではない)と自認しています。イラストはストレス発散も兼ね数日おきに作成しているため精力的かもしれませんが、一般的な趣味の範囲内と思います。
個人的には不安の強いADHDかと思っており、ADHDと思う根拠は以下です。
・頭の中に今していることに関係の無い考えがたくさんあり、すぐ他のことを考えて作業の手が止まったり、過去への後悔で落ち込んだりする。考え続けるので睡眠が苦手、意識を手放すことが怖い(寝るのに時間がかかる)
・一度集中すると途中でやめられず、半日以上稼働してることがある。
・忘れ物、物忘れが多い(家族も忘れ物が多い)
・時間を守ることが苦手で、予定を確認しても遅刻したり別日に行ってしまう。
・感情の起伏が大きく、波があり気分が移ろいやすい。
・成人するまで爪噛みが辞められなかった。
また、体格が小さく体力も人より劣るため、労働し続けることで疲れが蓄積していくのも就労できなくなる一因かもしれないと考えています。
現状の処方に大きく不満がある訳ではありませんが、診断名に納得がいかず、できればストラテラ服用に戻りたいと考えています。(朝起きやすい、腹痛がなくなるため)
双極性障害2型の診断が正しいのでしょうか。
林: 「医師からはAと診断されているが、自分としては診断はBだと思う。なぜなら自分には症状aはなく、症状bがあるからである」
「ADHD から双極性障害2型へと診断が変わり困惑しています」と題されたこの【4991】のご質問はこのパターンに一般化できます。そしてこのパターンの質問には正確な回答はまず不可能です。なぜなら、質問者が「診断はBである」という答えを求めていることは明白で、したがってBの根拠である症状bが自分にあることが強調され、Aの根拠である症状aは自分にないことが強調された質問文になっているからです。ですから、質問文の内容が事実であるという前提に立てば、「質問者の診断はBである」という答えになることは必然で、答えが必然ということは、それは質問として成立していないということです。
したがってこのパターンの質問では、質問者の診断名は「不明」ということになるのが常ですが、この【4991】のケースでは、
・過去にADHDと診断されたことがある
・双極性障害2型と診断した医師は、ADHDの診断を否定したわけではない。
という点が一般的なパターンとは異なっています。すなわち、双極性障害2型と診断した医師が否定したのはADHDの診断ではなく、質問者のADHDの症状へのストラテラの効果であって、そして質問者の希望の中心は「ストラテラ服用に戻りたい」ですから、質問の題は「ADHD から双極性障害2型へと診断が変わり困惑しています」ではなく「ストラテラが処方されなくなり困惑しています」が適切ということになるでしょう。
すると、現在の主治医の判断の中で、その正否を真に検討すべきものは、「双極性障害2型という診断」ではなく、「ストラテラが不要という判断」です。そして、この判断には、私は賛同できません。
なぜなら、質問者の症状に、現に事実としてストラテラが効いていたと思われるからです。現在の主治医は「ADHD症状が改善していないのであればストラテラはやめましょう。腹痛を抑える作用もないです。」とおっしゃってストラテラの処方を中止したとのことですが、これは、ADHDの症状とストラテラの効果についての非常に狭い考え方に基づく誤った判断だと思います。つまり、理論的にはどうであれ、この【4991】のケースでは現に事実としてストラテラの服用によっていくつもの症状が改善しており、かつ、副作用は軽度ですので、ストラテラを中止する理由はありません。他方、たとえ事実としてそのように改善していたとしても、理論的にはストラテラにはそうした作用はない以上、症状改善とストラテラの関係は偶然あるいは本人の思い込みにすぎず、したがってたとえ副作用が軽度だとしても、ストラテラを続けることは適切でないという考え方もあり得ます。しかしながらストラテラは、ADHDの中核症状だけでなく、ADHDに伴う症状、たとえば抑うつにも効果が見られることがあります。この事実は抽象的に考えると、
(1)ストラテラ
↓
(2)ADHDの中核症状の改善
↓
(3)対人関係等の改善
↓
(4)抑うつなどのADHDの2次的症状の改善
というメカニズムであると考えたくなりますが(つまり、抑うつをADHDによる対人関係の障害などの結果としての2次的症状であると位置づけたとき、対人関係が改善することによって抑うつが改善すると考えるのは論理的に正当で、その対人関係の改善は、ADHDの中核症状がストラテラで改善することの結果として得られる、というメカニズムです)、実際には上の(2)(3)を介さずに、(1)ストラテラが(4)抑うつを改善 することが期待できることが、脳科学的なデータに基づき理論的にも示されています(たとえばhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811913008501)。そうしますと、そもそもADHDに伴う抑うつが、必ずしも2次的症状のみであるとは限らないという可能性も発生しますが、それは今後の研究の発展を見ないと何とも言えないとしても、少なくとも、「ストラテラが抑うつを直接に改善する可能性がある」とまでは言えます。そしてこの【4991】の質問者の腹痛などの身体症状が、抑うつと関連して現れたものだとすれば、「ストラテラが腹痛に効いた」という質問者の主観的体験は、決して思い込みではなく、したがって、ストラテラの再開は治療的に十分に意味があると考えられるでしょう。
(2025.10.5.)