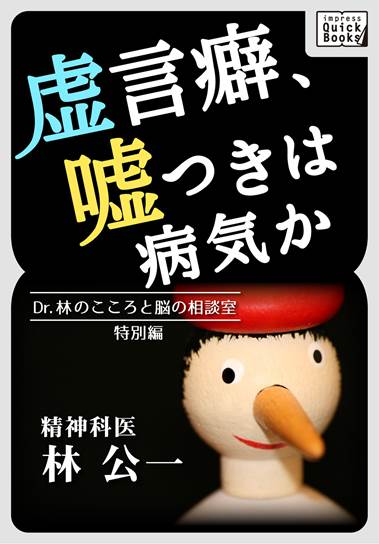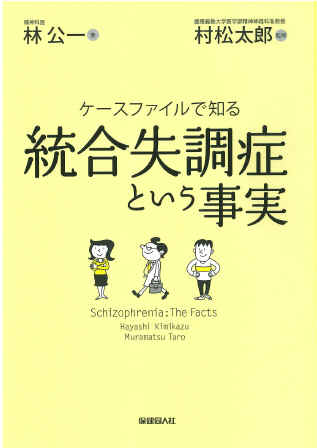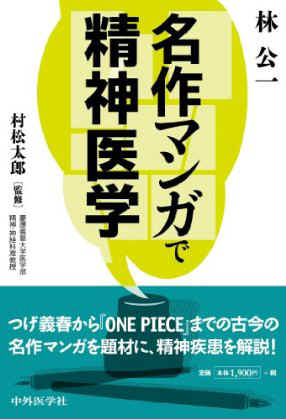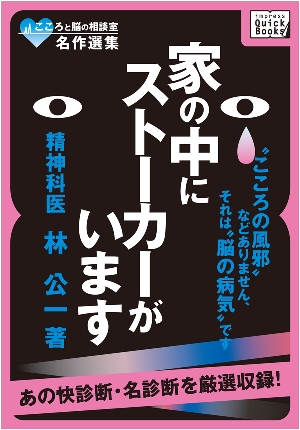【4990】 林先生の AI 回答の考察について
Q: 20代男性です。いつも興味深く当サイトを拝読しております。
私の質問は、
「林先生のAI回答の分析は部分的には正しいと思いますが、病名の提示の有無を“AIの方針”と解釈するのは一回の生成だけでは不十分であり、最低でも複数回(10回程度)生成して傾向を確かめる必要があるのではないか?」、
というものです。
林先生がお使いになったと思われる生成AIは「大規模言語モデル(LLM)」であり、膨大なテキストデータから統計的なパターンを学習し、その文脈に合いそうな語を確率的に並べています。
したがって「病名を出す」「病名を避ける」といった振る舞いは、結局のところ学習時の分布・アライメント・出力時のサンプリング手法に左右されます。
どれだけもっともらしい説明があっても原理的に考えて、生成AIは真に文章の意味を理解して回答しているわけではありません。
つまり、ある一回の生成で「統合失調症」などの病名を示したとしても、一貫したポリシーあるいは判断力の下で出力されたとはいえず、それがそのAIの「方針」や「本質的特性」を表すとは限りません。
AI回答【4969】緊急性の有無・考では、
>その理由はAIが「質問者がその行動に出るために「統合失調症」という病名を示すことが適切かどうかの判断」として、病名までは示さない方が適切であると考えたという解釈もできるが、この【4969】は統合失調症と断言するには情報不足であるから断定を避けたという解釈もできよう。
AI回答【2786】命を狙われ続けている・考では、
>その観点からすると、AIの回答は、形式上は本人に寄り添った形を取り、精神医学的にもかなり正確なものであるが、形式とは裏腹に、真に本人のためになる回答とは何かという観点は希薄であるように思える。
とあります。
上記のように林先生は1度きりのAI生成文章から、【4969】ではAIは病名を出さず【2786】では病名を出したことに注目し、AIの回答方針や特徴を比較しながら解釈・分析されています。
しかし実際には、同じプロンプトを複数回生成させれば、「病名を出すパターン」「出さないパターン」の両方が混在する可能性は十分あります。これはランダム性(サンプリングの揺らぎ)によるものであり、1回だけの観察からAI回答の「方針」や「意図」を読み取ると、外れ値を一般化するリスクがあります。
もしAIの回答傾向を評価するなら、最低でも同一プロンプトで複数回(10回以上が望ましい)生成し、具体的な病名の提示の有無や表現の違いをエクセルなどの表計算ソフトで場合分けをし、統計的に分析する必要がある、と考えます。
しかし、現実的には時間と手間が多大にかかりますし、実用性との兼ね合いも微妙です。研究的にAIの出力傾向を調べるのであれば有意義ですが、日常的にQ&Aの運営や個人の利用でそこまで繰り返すのは実用性に欠けるし、現実的に困難だといえます。
コラムでの林先生の考察は、AI回答の「親切さ」や「複数の観点からの説明」に注目する点では有意義ですが、一度きりの生成に基づいてAIの「方針」までを読み取るのは困難だと思います。
以上、いかがでしょうか?
林: AIについての質問者の記述には私は全く異論はありません。私も質問者と同じ認識です。
しかし、このご質問のポイントと思われるところの、
「林先生のAI回答の分析は部分的には正しいと思いますが、病名の提示の有無を“AIの方針”と解釈するのは一回の生成だけでは不十分であり、最低でも複数回(10回程度)生成して傾向を確かめる必要があるのではないか?」
については、林の奥に最近掲載したAIについての一連の文章の主旨について質問者が誤解されていることを示していると思います。その誤解が発生した理由の一端は私の文章の方にあると言えるでしょう。
誤解のポイントは、
病名の提示の有無を“AIの方針”と解釈する
という部分で、私はそのような解釈は一切していません。
当初から、私がそのように解釈しているという誤解を避けるために、
このAI回答シリーズの最初のコラムAI回答【4984】精神疾患と発話の明瞭さ・考 の冒頭に(他のコラムの冒頭にも同様に)、
精神科Q&A【4984】のQに対する回答を、AI(2025/09/15現在無料で公開されているAIの一つ)に求めてみた。
というように、「AI(2025/09/15現在無料で公開されているAIの一つ)」と特定し(つまり、あくまでもある一日におけるある一種類のAIの回答であって、”AIの方針”というAI一般の回答を論じるものではないことを示した)、AIの回答を紹介するにあたっては
そのAIは次のように回答した:
というように、「そのAI」としたのですが(つまり、あくまでそのAIの回答の紹介であって、AI一般の”方針”を論じるものではないことを示した)、こうして【4990】のご質問を受けてみて、こうした注意だけではまだまだ誤解されやすいということに気づきました。
しかしでは、誤解を避けるためにはどのように記せばいいかということになるとかなり難しく、いや、もちろん、とても不自然でまわりくどい書き方をすればできないことはないのですが(たとえば、「xx年xx月xx日の時点で無料公開されているAIの一つに、yy年yy月yy日yy時yy分yy秒に聞いてみた」のように書けば正確でしょう)、学術論文として書くのならともかく、コラムとしてはそこまでの厳密な表現は適切とは思い難いところです。
というわけですので、林の奥の文章を修正することはせず、ここに(【4990】への回答として)このように方針を記すことにとどめたいと思います。
【4990】の質問者には、貴重なご指摘をいただいたことに感謝いたします。
(2025.10.5.)