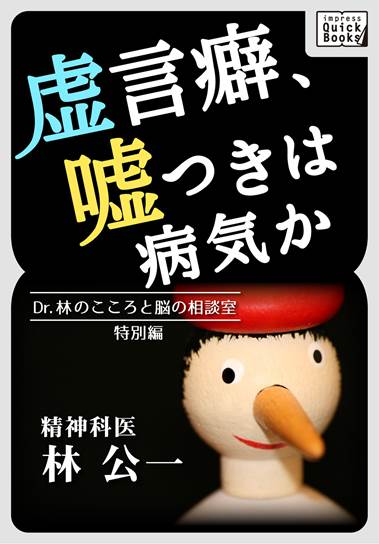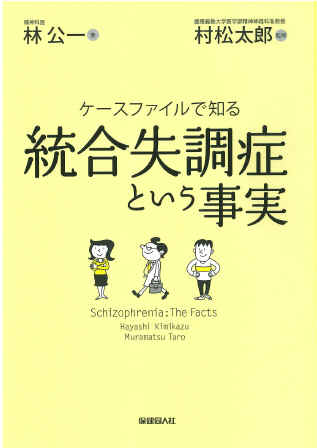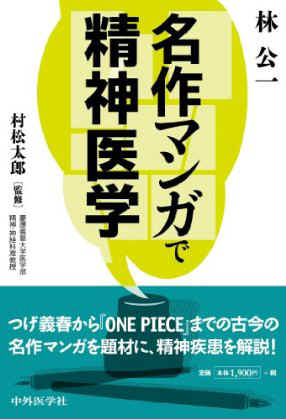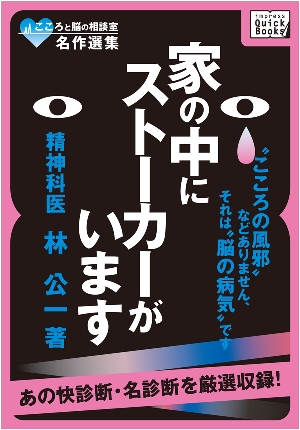【4945】自分の興味がわからないという症状が ASD に由来するものであるのかを知りたいです。
Q: 20代女性です。
幼い時に広汎性発達障害の診断を受け、療育に通っていましたが、現在は特に通院等はしていません。
現在大学4年生で、春から大学院に進学します。学部と同じ専攻で内部進学するのですが、特に研究をしたいというわけではなく、就活を始める学部3年時点で自分の将来やりたいことが定まっておらず、社会に出る前にもう少し自分のことを見つめる時間がほしいと思ったことが大学院進学を決めた主な理由です。
先月院試が終わり、無事に合格したのですが、このようなふわふわとした理由で進学を決め、やりたい研究テーマも定まっていない自分が大学院でやっていけるのかと不安になっています。院試の口頭試問で教授に言われたキツめの言葉を何度も思い出しては苦しくなったり、進学後に教授や先輩方の前で改めて卒論を発表せねばならないということを考えて憂鬱になったりと、考えても仕方がないとわかっていることを繰り返し考えてしまいます。
こうした大学院に対する不安にも悩んでおりますが、進学してしまえばどうにかなるとは思っており(カウンセリングを受けるべき等のアドバイスをいただければそれはそれで嬉しいです)、先生にお聞きしたいのは、このように不安を煮詰めながら自分について考えている中で改めて自覚した自分の特徴が、発達障害に由来するものであるのかどうかということです。その症状の対処法を知りたいというより、自分が悩んでいることの原因が、単なる怠惰さや無能さなどによるものではなく、発達障害によるものだと帰属させることで安心したいのだと思います。もしくは発達障害に関連するものではないとしても、世間一般の人々にもよくあることであるのかを知りたいです。
その特徴とは、自分が何に興味があるのかわからない、言語化できないということです。
研究テーマを定めなければならないと思い、自分の興味関心を探っているのですが、自分が何に興味があるのか、どういうことをやりたいのかがよくわかりません。興味がないこと、やりたくないことははっきりとあり、それらとの比較で自分が何に興味があるのかを模索しています。ミステリー小説を読んだりホラー映画を見たりするのは好き、などというレベルでは自分の興味関心がわかっており、まったく自分の興味や好き嫌いを認識できないわけではないので、自分が研究に向いていない単なる無気力な大学生であるのか、アレキシサイミアのようなものであるのか気になっています。
また、発達障害者の精神年齢は健常者の2/3であるというような話を聞いたことがあります。実際に、自らの興味をしっかりと自覚している同期たちに引け目を感じている今の自分も、過去の自分と比べれば明らかに成長できていると認識しており、他の人と比べずにマイペースに自分と向き合っていけばいいと思うようにしているのですが、実際のところ精神年齢が2/3であるというような話は正しいのかどうかも教えていただきたいです。
林:
自分の興味がわからないという症状が ASD に由来するものであるのか
これは難しいご質問です。YesとNoの両方があり得るので、どちらも正しいからです。
すなわち、「自分の興味がわからないという症状が ASD に由来する」場合があります。その意味ではYesです。
しかし他方で、「自分の興味がわからない」ことは、ASDでない人にもあり得ることです。その意味では「自分の興味がわからないという症状が ASD に由来する」とは言えませんからNoです。
なお
発達障害者の精神年齢は健常者の2/3である
それは全く根拠のないでたらめです。
(そもそも精神年齢という概念自体が、定義が曖昧で概念が薄弱なものです。過去においては学術的な用語としてよく使われていた時代がありましたが、現在ではほとんど使われることはありません)
(2025.4.5.)