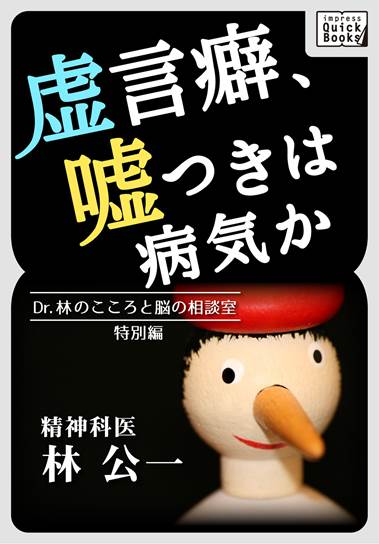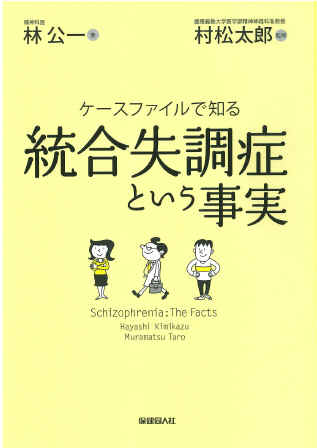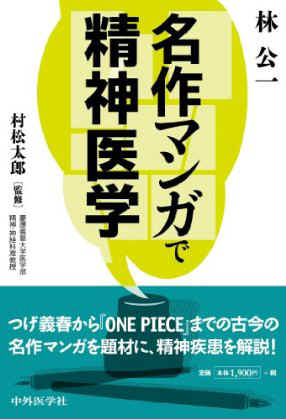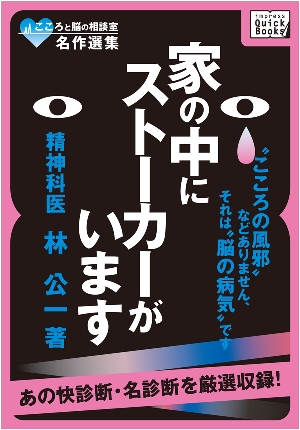AI回答【4994】医療を受けさせたい・考
AI回答【4994】独語と妄想の激しい職員に医療を受けさせたい. について、AI(2025/10/5現在無料で公開されているAIの一つ)に回答を求めてみた。【4994】のQは次の通りである。
***
【4994】独語と妄想の激しい職員に医療を受けさせたい
Q: 私は20代前半女性・役所の会計年度任用職員(パート勤務)です。
同僚である30代程度の女性・正規職員について質問いたします。以下、その職員をAとします。
Aは私と同じ課で別の係(以下X係)に属しており、私が登用されるより前から大きめな声での独語と被害妄想が多く他人に妄想を元に暴言を吐くため仕事が任せられず、X係長に支離滅裂な話を一方的に振って係長を困らせている存在だと聞いていました。
9月より私の係(以下Y係)が繁忙期に入り、会計年度職員の人数を増やしても人手が足りない時期になりました。Aは電話にはすぐ出て住民には暴言を吐かないため電話応対だけならと課長・X係長から駆り出される形でY係に来ました。
Aはこちらに来て最初の週に以下の問題を起こしました。
①私に対して「若いから結婚したり子供作ったりするんだろうけれど私はそういう制度に反対しているからしない。私はそういうの願い下げだが頑張れ」と発言。
②Y係長に対して面と向かって「影響力のない人」と発言。
③産休中の職員宅に送る荷物を送る手配の指示を「私はあの人の悪い噂を知っているからあの人と関わりたくない。郵送の手配も関わることになるからしない」と拒否。Y主任が指示を撤回した後も産休職員に関する「悪い噂」について汚い言葉でひたすらY係長に説き、最終的に大声で自分の主張をして泣いて帰る。
①について、私は難病で子供を望むには難しい状況にあり、そもそも20代前半の未婚の人に対して結婚や出産についての話題を振るのはどうかと思ったためY係長に相談しました。
③の事件のあとX係長から、「Aは数年前から精神的に問題があり、X係に来る前は短期間でいくつもの部署を転々としていた。ここに異動した当初から何度も受診を勧めているが全く治療する気がない状態だ」と伺いました。また、課長曰くどうしても処分は難しいようで、上に報告済みだが現時点でどうすることも難しいとのことです。一方で同じような発言があればすぐに動くとお話していただきました。
なお③翌日にY係に来た際、「以前から心身に不調があり、その影響が出てしまった」とA本人が話していました。その後は相変わらず何も任されていない状態で独語とため息が多くあり、駆り出された理由である電話応対についても疑問が残る対応が出てきています。
前置きが長くなりましたが質問は3点です。
1.受診するよう何度も伝えても受診しない場合、上司などの家族ではない人が強制的に連れていくことは可能なのでしょうか。
2.受診する気がないのに心身の不調を自覚する状態はあり得ますか。
3.措置入院などは目立った他害(暴行など)がないと難しいのでしょうか。
***
AIは次のように回答した。
長文と詳細な状況説明をありがとうございます。非常に大変な状況で、質問者様が冷静に対応策を検討されていることに敬意を表します。
職場の正規職員であるA様の行動は、同僚として不安やストレスを感じるだけでなく、業務の円滑な遂行にも影響を及ぼしており、非常に深刻な問題だと認識しています。
ご提示の状況とご質問は、精神保健福祉法と職場の安全配慮義務に関わる専門的な内容を含みます。私はAIであり、法律や医療の専門家ではありませんので、具体的な法的なアドバイスや診断はできません。しかし、一般論として、日本の制度に関する情報に基づいて、3つの質問について解説します。
1. 受診に関する強制力について
Q. 受診するよう何度も伝えても受診しない場合、上司などの家族ではない人が強制的に連れていくことは可能なのでしょうか。
A. 原則として、家族や上司などが本人の意思に反して強制的に精神科を受診させることはできません。
• 精神科医療の原則: 精神科の受診・入院は、本人の同意に基づく「任意入院」が基本原則です。これは、精神疾患を持つ人の人権を最大限尊重するためです。
• 例外的な強制受診(措置入院の検討): 強制的な受診を唯一可能にするのは、後述する措置入院や医療保護入院などの手続きの「前段階」として行われる診察です。
◦ 措置入院の要件を満たすか判断するために、「自傷他害のおそれ」が疑われる場合、市長村長または知事は、本人の同意なしに指定医の診察を命じることができます(精神保健福祉法第27条など)。
◦ しかし、これは上司の判断ではなく、警察、消防、家族、または保健所などが**「明らかに自傷他害のおそれがある」**と判断し、自治体(知事や市長)に届け出て、自治体が公権力として動く場合に限られます。
• 職場としての対応: 職場としてできることは、業務命令として産業医や指定された医療機関での受診を強く勧奨・指示することや、休職を命じることです。ただし、この受診もあくまで診断・評価のためであり、治療の強制ではありません。A様が正規職員であるため、服務規程に基づく対応(業務命令違反、安全配慮義務違反など)が主となります。
2. 心身の不調の自覚と受診の意思について
Q. 受診する気がないのに心身の不調を自覚する状態はあり得ますか。
A. はい、大いにあり得ます。
• 病識と治療意欲の分離: A様が「心身に不調がある」と話されたことは、自身の状態が悪化していることの自覚(病識)があることを示唆します。しかし、病識があることと、専門家の助けを借りて治療を受けようとする意欲(治療意欲)があることは、必ずしもイコールではありません。
• 治療への抵抗: 精神疾患を抱える方の中には、以下のような理由から治療に強い抵抗を示す方が多くいます。
◦ 病気と認めると、自分自身が崩壊してしまうという強い恐怖感。
◦ 自分の弱みを知られることへの羞恥心や抵抗感。
◦ 薬物療法や精神療法に対する誤解や不信感。
◦ **「自分は間違っていない」「周りが悪い」**という強い思い込み(妄想など)のため、自分が治療の対象であることを受け入れられない。
• A様の場合、「以前から心身に不調があり、その影響が出てしまった」と話すことで、一時的に周囲の理解を得ようとする、あるいは自分の行動の理由付けをする意図も考えられます。しかし、受診の意思がないのは、上述のような治療への抵抗感が極めて強いためと推測されます。
3. 措置入院の要件について
Q. 措置入院などは目立った他害(暴行など)がないと難しいのでしょうか。
A. 措置入院は非常に厳格な要件が設けられており、「目立った他害」がないと難しいのが現実です。
• 措置入院の要件: 措置入院(精神保健福祉法第29条)は、「精神障害のために、自傷または他害のおそれがある」と、2名以上の指定医が一致して診断した場合に、都道府県知事の決定によって行われる強制入院です。これは人権に強く関わるため、非常に慎重に運用されます。
• 「他害のおそれ」の具体的な例: 「他害のおそれ」は、単なる迷惑行為や暴言ではなく、生命・身体に危険を及ぼす具体的で差し迫った行為を指します。
◦ 例: 暴行、器物損壊、殺人や放火の予告、ストーカー行為、自殺を伴う他者への危害など。
• A様の状況の評価:
◦ 「支離滅裂な話を一方的に振る」「影響力のない人などと暴言を吐く」「大声で泣いて帰る」といった行為は、「職場の秩序を乱す行為」であり「業務上の他害」と言えますが、法律上の「他害のおそれ」(生命・身体への危険)と判断されるにはハードルが高いのが実情です。
◦ 現在、A様が行っている行為が、直接的な暴行や、生命を脅かすような行為にエスカレートしない限り、措置入院の適用は極めて難しいと言わざるを得ません。
現時点で職場として検討すべき対応
A様への対応は、**「公務員の服務規程に基づく対応」と「職場環境の維持」**という2つの視点から行うことになります。
1 記録の徹底と報告の継続:
◦ A様の**「独語とため息が多い」「電話応対についても疑問が残る対応」などの業務上の問題、そして「暴言」「業務拒否(産休職員の件)」「個人的な発言(結婚・出産)のハラスメント**」に該当する可能性のある発言を日時・場所・内容を詳細に記録し続けてください。
◦ 課長・Y係長にその都度報告し、「同じような発言があればすぐに動く」という課長の方針に基づき、速やかな対応を求めてください。
2 ハラスメント・人権侵害としての対処:
◦ 特に、個人的な事柄(結婚・出産・難病)に関する不用意な発言は、ハラスメントや人権侵害に該当する可能性があり、公務員倫理としても問題です。Y係長に相談した上で、人事部門やハラスメント相談窓口に正式に相談し、公的な問題として扱ってもらうよう働きかけることが重要です。
3 業務の切り分けと安全配慮:
◦ 現状、A様に重要な業務は任されていないとのことですが、他の職員(特に質問者様ご自身)の業務負担が増えすぎないよう、課として人員配置の見直しを続ける必要があります。
◦ A様の言動が質問者様への心理的負荷となっていることを上司に再度伝え、直接的な接触や不必要な会話を減らせるよう、席の配置や業務の分担を見直してもらうことも重要です。
公的な機関である以上、服務規程と人事上の手続きに従って、記録と報告を積み重ねることが、最終的にA様を治療へ繋げるか、または休職・異動といった措置を行うための唯一の手段となります。ご自身を責めず、ご自身の心身の安全を最優先にしてください。
【4994】の3つの質問のうち、質問1 (1.受診するよう何度も伝えても受診しない場合、上司などの家族ではない人が強制的に連れていくことは可能なのでしょうか)は精神病性障害(統合失調症と妄想性障害がその代表である)をめぐって周囲の人からしばしば発せられる質問である。すなわち、当事者本人はその症状の結果として周囲に相当な迷惑をかけているが、病識が全くないかほとんどなく、自分は病気ではないと言い張り、どうしても精神科を受診しようとしない。周囲としては、本人のためにも、また周囲の人々のためにも何とかして受診させたい。強制的にでも受診させる方法はないのだろうか、というのが質問である。
林は次のように回答した(【4994】の回答より)
***
まず不可能です。【4843】未治療の統合失調症の友人を、何とか医療に繋げたい などをご参照ください。
***
これはいわば精神科Q&A特有の回答のスタイルで、類似の質問が過去の精神科Q&Aにある場合には、その参照を勧めるというものである。
対比してAIの回答を見ると、回答を独立したものとしてみた場合はAIの回答の方が丁寧でまとまっている。精神科 Q&A特有のスタイルをAIは取るわけにはいかないから当然ではあるが、独立した回答として見れば、AIの方がはるかに優っていると言えよう。また、 AIは、質問文を単独のものとして回答するのではなく(単に「質問1」に答えるのではなく)、質問全体を読んで、その中での質問1の位置づけを十分に考慮している。それは回答の中の次の記述に表れている。
• 職場としての対応: 職場としてできることは、業務命令として産業医や指定された医療機関での受診を強く勧奨・指示することや、休職を命じることです。ただし、この受診もあくまで診断・評価のためであり、治療の強制ではありません。A様が正規職員であるため、服務規程に基づく対応(業務命令違反、安全配慮義務違反など)が主となります。
林の回答も、質問全体の中での質問1の位置づけを考慮することはしている。質問1に回答する前のこの部分である。
***
課長曰くどうしても処分は難しいようで、上に報告済みだが現時点でどうすることも難しいとのことです。
職場のスタッフのみならず、役所のサービスを受ける人々にも多大な迷惑をかけている状態ですから、「現時点でどうすることも難しい」というのは、むしろ職場が組織しての責任を果たしていないと言うべきでしょう。
***
このように林も質問1の背景に言及しているが、「職場が組織しての責任を果たしていない」と批判的な指摘するにとどまっている。それに対してAIは職場としての具体的な対応を示しており、林よりも建設的な回答であると言えよう。
質問2についての論考は省略する。
AIがどう回答するか、私が最も関心を持っていたのは措置入院についての質問3である。措置入院は、法律の文言上はシンプルで、法文だけを読めば納得しやすいものであるが(但し、「いかなる場合でも強制入院は許されない」という立場を取った場合は納得できないであろう。しかしそうであれば、「納得できない」という点でわかりやすい法律であると言える)、実務上は複雑で難解な問題が多々ある。したがって質問3に的確に答えるためには、単に法律の条文についての知識だけでは全く不十分で、現代の日本社会でこの法律がどのように運用されているかという実態についての知識が必要である。AIはどこまでそうした知識を持っているのか。
そういう関心を持って私はAIの回答に注目したのであるが、AIの上記の回答はきわめて正確で、かつ、【4994】のAさんの状況に具体的にあてはめたときの措置入院の考え方にも的確に言及していた。法律について現代のAIが持っている知識は、単なる紙の上の抽象的なものではなく(「紙の上の」という表現はもはや時代遅れだがあえてここでは用いてみた)、実務にも相当に及んでいるというのはすでに常識に属することであるが、こうして実例に接してみると、AIの偉大さがありありと感じられる。
AIの回答はさらに、【4994】の質問者の職場でできる具体的な方策をわかりやすくまとめている。
そしてもちろんAIの回答の常の通り、質問者の立場に十分に共感するトーンが回答全体に流れている。
こうして見ると、【4994】の回答は林よりもAIの方が明らかに優れていると言える。しかもAIは質問すれば瞬時に回答してくれる。精神科Q&AでなくAIに質問した方がよかったのではないか。【4994】の質問者がAIの回答を読んでどう感じられたか、ぜひ知りたいところではある。
(2025.10.6.)