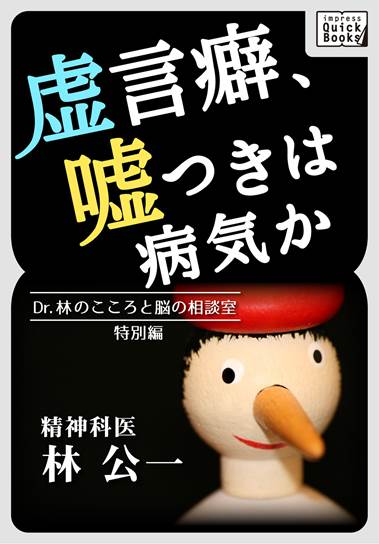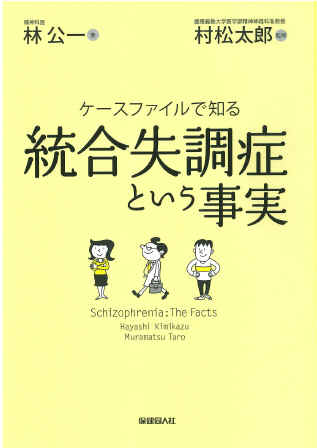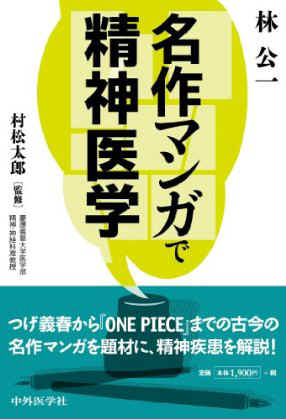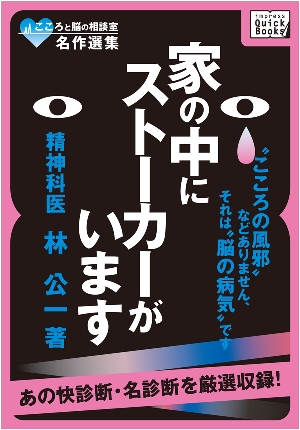AI回答【4993】私は二重人格ですか・考
「二重人格」という言葉は昔からある。関連する医学用語として「解離性同一性障害」(「解離性同一症」も完全に同義)があり、二重人格はその中の一つのタイプを指す言葉として位置づけられるが、昔からある言葉と現代の医学用語は、重なる部分が多々あってもかなり異なるのが常で、「二重人格」と「解離性同一性障害」もその例にもれない。したがって二重人格についての質問に対してはこの問題についての留意が必要になるが、AIはこの点をどうクリアするのか。そこで【4993】私は二重人格ですか?について、AI(2025/10/7現在無料で公開されているAIの一つ)に回答を求めてみた。【4993】のQは次の通りである。
***
【4993】私は二重人格ですか
Q: 20代前半女性です。解離性障害と診断されています。私は二重人格なのでしようか?
1年前に自殺未遂をした後に不思議な症状がありました。自殺未遂後、母親が精神科の診察に同席した際、母親を心配させたくないという気持ちが浮かびました。
すると、その瞬間突然スイッチが入ったかのようにテンションが上がり、私の意思とは別に私がペラペラと勝手に話始めました。口調が幼くなっているとも主治医に指摘されました。
その時の私は自分の事を斜め後ろから観測しており、「恥ずかしいからやめて!」と思っていました。
別の日も友人と話してる時に同じような現象が起きました。
それ以降も解離が起きている時は母に「幼児退行している」と言われました。これは私の中にもう1人、人がいるということでしょうか?
***
AIの回答は次の通りであった。
大変つらいご経験をされたこと、そしてご自身の症状について深く悩んでいらっしゃるお気持ち、お察しします。
ご質問の「私は二重人格なのでしょうか?」についてですが、まずはご自身が医師から「解離性障害」と診断されているという点が最も重要です。
「二重人格」と「解離性障害」について
1. 「二重人格」という言葉について
「二重人格」という言葉は、医学的には現在あまり使われていません。これに近い症状を持つ病名は、**解離性同一症(Dissociative Identity Disorder, DID)**と呼ばれます。これは、解離性障害の1つのタイプです。
2. 解離性障害の「解離」とは
解離性障害の「解離」とは、ある体験や感情、記憶、自己意識などが、自分自身の意識や思考から一時的に切り離されてしまう状態を指します。
ご相談者様が経験されている
• 突然スイッチが入ったようにテンションが上がり、意思とは別にペラペラ話し始める
• 口調が幼くなる
• 自分のことを斜め後ろから観測している感覚
• 「幼児退行している」と言われる
といった症状は、解離性障害、特に自己の意識や行動の一部が自分のものではないかのように感じられる解離性同一症(あるいはそれに近い特定不能の解離性障害)の一部の症状として説明される可能性があります。
3. 「もう1人、人がいる」という感覚について
ご質問の「これは私の中にもう1人、人がいるということでしょうか?」についてお答えします。
解離性同一症では、「別の人格」(専門的には交代人格や解離パートと呼ばれます)が出現し、そのパートが行動や意識を支配することがあります。
しかし、「もう1人、人がいる」という感覚は、必ずしも厳密な意味で「完全に独立した人格が内側に存在している」というわけではありません。むしろ、ご自身の持ついくつもの側面や役割(例:頑張り屋の自分、弱い自分、子どものような自分など)が、強いストレスや感情の危機に直面した際に、一つのまとまった「私」の意識から切り離され、独立した形で表に出てくる現象だと捉える方が、治療上は適切とされています。
大切なこと:主治医との連携
ご自身の状態について最も正確に把握し、適切な診断と治療を行えるのは、あなたを**「解離性障害」と診断した主治医の先生**です。
• 今回話してくださった具体的な症状(斜め後ろからの観測、スイッチが入ったような言動、幼い口調など)を、ぜひ主治医の先生に詳しく話してみてください。
• 「私は解離性同一症なのでしょうか?」「私の症状は、私の中の複数の側面が切り離されて出てきている状態なのでしょうか?」といった具体的な質問を投げかけてみることも大切です。
主治医の先生と一緒に、ご自身の症状がどのようなメカニズムで起こっているのかを理解していくことが、治療の第一歩になります。
何か少しでも、ご自身の気持ちが楽になる手がかりになれば幸いです。
精神医学的観点からは、「二重人格」をめぐるこの【4993】の回答におけるポイントは2つある。第1は「解離性同一性障害(解離性同一症)」との関係。第2は「別人格」の意味である。
第1の点についてのAIの回答は正確かつ模範的である。まず「二重人格」が正式な医学用語ではないことを「医学的には現在あまり使われていません」というソフトな表現で示し、「これに近い症状を持つ病名」として「解離性同一症(解離性同一性障害も同一)」を紹介することから始める。そして「解離性同一症」が「解離性障害の1つのタイプ」であることを言う。そして「解離」を「ある体験や感情、記憶、自己意識などが、自分自身の意識や思考から一時的に切り離されてしまう状態を指します」と簡潔かつ正確に説明する。流れるような説明手順である。そしてAIはここまでを前提知識として示したうえで、【4993】の質問者の具体的な体験(症状)について、「・・・といった症状は、解離性障害、特に自己の意識や行動の一部が自分のものではないかのように感じられる解離性同一症(あるいはそれに近い特定不能の解離性障害)の一部の症状として説明される可能性があります。」と回答している。これは実に正確な回答である。
一方、当該部分についての林の回答は次の通りである。
***
「二重人格」(あるいは「多重人格」)は、現代の精神医学用語では「解離性同一性障害」にあたります。質問者はご自身の体験について
それ以降も解離が起きている時は
と表現しておられますので、ご自身の体験が「解離」であることは認識しておられるのだと思います。そのご認識は正しいです。
解離性同一性障害は、解離の症状の一つです。解離の体験(症状)が、ある一定の基準を満たしたときに、解離性同一性障害と診断されることになります。その意味でこの【4993】のケースは、解離性同一性障害とは診断できません。解離性同一性障害の診断基準を満たさないからです。
***
林とAIの回答の最も大きな違いは、【4993】の質問者が解離性同一性障害である可能性を、林は否定、AIは肯定している という点である。少なくともそのように読める。しかし精密に読めば、林とAIの回答はほぼ同じであると言える。両者の回答は、文言通りに引用すれば次の通りである。
解離性同一性障害とは診断できません ・・・ 林
解離性同一症(あるいはそれに近い特定不能の解離性障害)の一部の症状として説明される可能性があります・・・ AI
林は、質問者の症状が、解離性同一性障害の診断基準を満たさないことから、その診断を否定している。すると林が正しいのであればAIは誤りということになりそうだが、質問者の症状のすべてがメールに書かれているとは限らず、質問者にはさらに別の症状もある可能性があるから、その意味では「解離性同一症の一部の症状として説明される可能性があります」と言えるし、仮にすべての症状をあわせても解離性同一性障害の診断基準を満たすには至らなかったとしても「それに近い特定不能の解離性障害」であるとまではほぼ確実に言える。
こうしてみると、AIは、何気ない書き方であるが、解離の本質や解離性同一性障害の診断基準の細かい点のすべてを正確に理解したうえで、平易な表現で非常に正確な回答をしていることがわかる。
第2の「別人格」について、林の回答では強く注意を喚起している。まず回答の冒頭で
***
「私は二重人格」と「私の中にもう1人、人がいる」は同一ではありません。質問文からは質問者がこの二つを同一と考えておられる可能性が読み取れますが、そうだとすれば質問者の認識は誤っています。
***
と述べ、回答の最後を
***
「私の中にもう1人、人がいるということでしょうか?」については、文学的なレベルで答えるのであれば肯定できるかもしれませんが、医学的な意味での二重人格や解離性同一性障害は、「私の中にもう1人、人がいるということ」とは全く意味が異なります。人の中に別の人が存在することはあり得ません。
***
と結んでいる。
これは正しい回答であるが、あらためて読み直してみると、冒頭と結びは全く同じことを言っているにすぎない。同じこととはつまり、「私の中にもう1人、人がいる」という表現には重大な誤解がある、という指摘である。
AIは
「もう1人、人がいる」という感覚は、必ずしも厳密な意味で「完全に独立した人格が内側に存在している」というわけではありません。
と答えている。ここまでは林の回答と同じと言っていいかもしれない。
ただAIはさらに続けて次のように丁寧に説明している。
むしろ、ご自身の持ついくつもの側面や役割(例:頑張り屋の自分、弱い自分、子どものような自分など)が、強いストレスや感情の危機に直面した際に、一つのまとまった「私」の意識から切り離され、独立した形で表に出てくる現象だと捉える方が、治療上は適切とされています。
林の回答の「人の中に別の人が存在することはあり得ません。」
と
AIの回答の「必ずしも厳密な意味で「完全に独立した人格が内側に存在している」というわけではありません」
は
同じと言っていいものであるが、「別の人」や「完全に独立した人格」とは実のところ何を意味しているのかはこれだけではわからない。AIはそれを「ご自身の持ついくつもの側面や役割(例:頑張り屋の自分、弱い自分、子どものような自分など)が、強いストレスや感情の危機に直面した際に、一つのまとまった「私」の意識から切り離され、独立した形で表に出てくる現象」と具体的に説明している。但し、「「完全に独立した人格が内側に存在している」というわけではありません」が事実についての言及であるのに対し、「ご自身の持ついくつもの側面や役割(例:頑張り屋の自分、弱い自分、子どものような自分など)が、強いストレスや感情の危機に直面した際に、一つのまとまった「私」の意識から切り離され、独立した形で表に出てくる現象だと捉える方が、治療上は適切とされています。」は考え方についての言及であるので、厳密にはAIのこの説明の前段と後段は論理的繋がりが緩い。ここで「ご自身の持ついくつもの側面や役割(例:頑張り屋の自分、弱い自分、子どものような自分など)が、強いストレスや感情の危機に直面した際に、一つのまとまった「私」の意識から切り離され、独立した形で表に出てくる現象です」と言い切るのであれば前段と後段の論理的繋がりは保たれるが、あえて「だと捉える方が、治療上は適切とされています。」と論理を崩した理由は謎である。この文脈では論理を崩したほうが「人間的」な感じはするが、AIはそこまで考えて「人間的」な回答を選択したのか。また、私が考えるところによれば、「ご自身の持ついくつもの側面や役割(例:頑張り屋の自分、弱い自分、子どものような自分など)が、強いストレスや感情の危機に直面した際に、一つのまとまった「私」の意識から切り離され、独立した形で表に出てくる現象」は、決して「だと捉える方が、治療上は適切」かどうかというレベルの話ではなく、「ご自身の持ついくつもの側面や役割(例:頑張り屋の自分、弱い自分、子どものような自分など)が、強いストレスや感情の危機に直面した際に、一つのまとまった「私」の意識から切り離され、独立した形で表に出てくる現象である」と言い切ることが十分に事実として正しいと思うが(少なくとも、「自分の中に別人格が存在する」とするよりははるかに正しいはずである。しかし文学的な表現としては「自分の中に別人格が存在する」も誤りとは言えないので話は複雑になるが)、AIはそうは考えなかったということか、すると事実認識のレベルで林には誤りがあるということになるのか。そうかもしれないというのが怖いところではある。
なおAIは、回答の結びに「大切なこと:主治医との連携」として、質問者への現実的かつ適切なアドバイスを示している。この回答に限らず、「質問者への気遣いを決して忘れない」のは、AIによる回答のすべてに共通する性質であると言えるようである。それに対して精神科Q&A は、【2415】林先生は断定的すぎるし、思いやりに欠けます。もう少し理解ある態度で回答してください。の回答にも明記した通り、事実が質問者にとって希望の持てるものであれ、絶望しかもたらさないものであれ、常に事実を回答するのが基本方針であって、回答を読んだ読者が苦悩の淵に追いやられるかもしれないなどということについては一切考慮しないものであるから、質問者への気遣いという点ではAIの回答と対極にあると言えよう。
(2025.10.7.)